非認知能力の育て方|親が今すぐできる実践方法
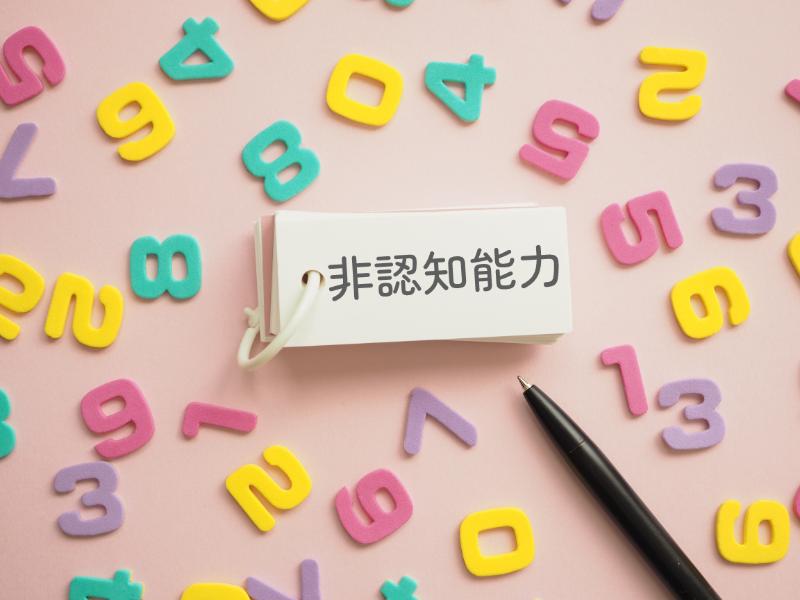
「非認知能力」という言葉をご存じですか?
計算力や読解力などのテストの点数で測れる「認知能力」と違って、「非認知能力」は具体的にどんな能力か、わからない方も多いかもしれません。
これからの時代を生き抜く子どもたちにとって、テストの点数で測れる「認知能力」と同じくらい、あるいはそれ以上に「非認知能力」が重要だと言われています。
そこで本記事では、非認知能力とは何かを具体的に説明し、家庭でどのように子どもたちの「非認知能力」を育むことができるのか、すぐに実践できる具体的な方法を紹介します。
この記事が、お子さんの「非認知能力」を育むための一助となれば幸いです。
非認知能力とは
非認知能力とは、学力テストでは測ることのできない能力のことを指します。
非認知能力にはさまざまなものがありますが、本項目では以下の5つの非認知能力をピックアップして紹介します。
- やり抜く力
- コミュニケーション能力
- 問題解決能力
- 自己肯定感
- 折れない心(レジリエンス)
それぞれの能力について詳しく見ていきましょう。
やり抜く力
やり抜く力とは、目標達成のために困難に立ち向かい、粘り強く努力を続ける力のことです。目標を達成するためには、壁にぶつかったり、失敗を経験したりすることもあるでしょう。そのような困難な状況に直面しても、諦めずに努力を続けることで、最終的に目標を達成することができます。
やり抜く力は、単に我慢することとは異なります。困難や壁にぶつかっても、なぜ乗り越えたいのかという目的意識を持つこと、そして、どのように乗り越えるのかという具体的な方法を考えることが重要です。目標達成のために試行錯誤を繰り返し、工夫しながら粘り強く取り組むことが、やり抜く力を育むことにつながります。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は、社会生活で不可欠なスキルで、円滑な人間関係や良好な社会生活に重要な役割を果たします。子どもにとって、この能力は学習や生活の場面で大いに役立つでしょう。
コミュニケーション能力は、「聞く力」「話す力」「読む力」「書く力」の4つの要素から成り立っています。これらは互いに関連し、影響し合います。例えば、相手の話をきちんと「聞く」ことで、適切に「話す」ことができ、たくさん「読む」ことで語彙が増え、「書く」力や「話す」力も向上します。
問題解決能力
問題解決能力とは、困難に直面した際に解決策を見つけ、実行する能力のことです。この能力は、子どもが将来社会で生きていくために重要です。
現代社会は急速に変化し、予測できない出来事が多いため、問題解決能力を持っていれば、柔軟に対応し、困難を乗り越えることができます。
自己肯定感
自己肯定感は、子どもの非認知能力の土台とも言える重要な要素です。自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、「自分は大切な存在だ」と思える感覚のことです。
自己肯定感が高い子どもは、困難に直面しても「きっとできる」と自分を信じ、積極的に挑戦できます。失敗しても、「次は頑張ろう」と前向きに捉え、くじけずに努力を続けることができるのです。
逆に、自己肯定感が低い子どもは、新しいことに挑戦することを怖がったり、失敗を必要以上に恐れたりして、自分の可能性を狭めてしまう可能性があります。そのため、子どもの自己肯定感を育むことは、他の非認知能力を伸ばす上でも非常に重要です。
折れない心(レジリエンス)
折れない心、すなわちレジリエンスとは、単に「我慢強い」「ポジティブ思考」であることとは異なり、困難な状況や逆境に直面した際に柔軟に適応し、乗り越えていく力のことです。困難にぶつかっても、そこから立ち直り、成長の糧にできるため、子どもの将来にとって非常に重要な能力です。
レジリエンスが高い子どもは、失敗を恐れずに挑戦し、目標に向かって粘り強く努力することができます。また、ストレスやプレッシャーにうまく対処し、精神的な健康を維持することも可能です。
この力は、先天的なものではなく、経験や環境を通して後天的に育むことができます。子どもが困難に直面した際に、どのようにサポートするかが重要です。
これらの能力は、学校での学習だけでなく、社会生活や仕事など、人生のあらゆる場面で重要になります。非認知能力を育むことで、子どもたちは困難を乗り越え、目標を達成し、より豊かな人生を送ることができるようになるでしょう。
後ほど紹介する方法を通して、お子さんの非認知能力を伸ばすため、家庭でできることから始めてみましょう。
子どもの非認知能力はなぜ重要なのか

子どもの非認知能力は、将来の可能性を広げる重要な要素です。高い非認知能力は、以下のようにさまざまなメリットをもたらします。
- 勉強が好きになる、集中力が続くようになる。
- 友達と仲良くできる、自分の気持ちを上手に伝えられるようになる。
- 難しい問題にぶつかったときに、諦めずに解決策を見つけられるようになる。
- 失敗してもくじけずに、前向きにチャレンジできるようになる。
- 自分を好きになり、幸せな気持ちで毎日を過ごせるようになる。
このように、非認知能力は社会で成功し、充実した人生を送るために欠かせない力です。特に幼少期における土台づくりが、その後の成長を大きく後押しします。
非認知能力は幼少期に大きく育まれるものですが、大人になってからも伸ばすことが可能です。子どもが小さいうちにしっかりとした土台を作ることは重要ですが、親も子どもと一緒に非認知能力を育てることで、子どもの未来の可能性をさらに広げることができます。
非認知能力が高い子どもの特徴
非認知能力が高い子どもは、以下のような特徴を持つことが多いです。
- 挑戦することを恐れない
- 周囲と協力して物事を進められる
- 自分の気持ちを適切に表現できる
- 感情をコントロールできる
- 困難にぶつかっても諦めずにやり抜く
- 好奇心旺盛で新しいことに意欲的に取り組む
これらの特徴を持つ子どもは、さまざまな状況に柔軟に対応し、成功を収める可能性が高いと言えるでしょう。
家庭でできる非認知能力の育て方

家庭では、日常のさまざまな場面を通して、子どもの非認知能力を育むことができます。
- 子ども自身に目標設定させる
- 質の良い会話をする
- 遊びや日常生活の中で挑戦を促す
- ありのままを受け止めて認める
- 自分で考え、行動する機会を増やす
これらのポイントを詳しく見ていきましょう。
子ども自身に目標設定させる
目標を設定することは、子どもが「やり抜く力」や「問題解決能力」を身につける上で非常に重要で、自己肯定感を高めることにもつながります。
目標は子ども自身で設定させることが大切です。親が良かれと思って一方的に決めてしまうと、子どもは目標達成への意欲を育みにくくなってしまうため注意してください。無理強いせず、子ども自身が「やってみたい」と思える目標設定をサポートすることが、非認知能力を育む上で重要です。
例えば、子どもが「逆上がりができるようになりたい」と言ったとします。いきなり完璧な逆上がりを目標にするのではなく、「まずは鉄棒にぶら下がれるようになる」「鉄棒に足をかけられるようになる」など、小さなステップに分解してみましょう。そして、それぞれのステップをクリアするごとに「前回より長くぶら下がれているね!」「足を高くかけられるようになったね!」と、努力の過程を認め、褒めてあげることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで子どもは自信をつけ、最終的な目標達成へと近づいていきます。親は子どもの挑戦を温かく見守り、励ましながら、自己効力感を高めてあげましょう。
質の良い会話をする
子どもとの会話は、非認知能力を育むためにとても大切です。会話を通じて、子どもは自分の考えや感情を整理し、表現する力を育みます。また、親との良好なコミュニケーションは、子どもの自己肯定感を高め、安心感を与えます。
会話は長さでなく、質が重要です。質の良い会話をするためには、まず子どもに積極的に質問してみましょう。例えば、「今日、学校で何が一番楽しかった?」と具体的な質問をすることで、子どもはより深く考え、表現する機会を得ます。
次に、子どもの話にしっかり耳を傾けましょう。相槌だけでなく、子どもの気持ちに共感し、理解を示すことが大切です。例えば、「それは大変だったね」「すごいね、頑張ったね」など、子どもに寄り添う言葉をかけることで、子どもは安心して自分の気持ちを表現できます。
さらに、親自身が感情豊かに表現することも重要です。喜怒哀楽を素直に表現することで、子どもは感情を表現する方法を学び、共感力が育まれます。親の表情や声のトーンも子どもに大きな影響を与えるため、笑顔で話し、真剣に耳を傾けることで、子どもはコミュニケーションを楽しみ、信頼関係を築くことができるでしょう。
これらを意識することで、短い時間でも質の高い会話をし、子どもの非認知能力を育むことができます。
遊びや日常生活の中で挑戦を促す
遊びや日常生活の中で子どもに「挑戦」を促すことは、非認知能力、特に問題解決能力ややり抜く力を育む上で非常に効果的です。
子どもにとって、遊びや日常生活は最も身近な学びの場です。些細なことでも、子ども自身にとって新しい経験となるように工夫してみましょう。
例えば、少し難しいパズルに挑戦させてみましょう。すぐに答えを教えるのではなく、子どもが自分で考え、試行錯誤する時間を与えることが重要です。子どもが行き詰まっている様子であれば、ヒントを与えたり、一緒に考えたりすることで、子ども自身で答えを見つけ出す喜びを体験させてあげましょう。
また、日常生活の中でも、子どもに役割を与えるのもおすすめです。例えば、料理の手伝いを頼む、洗濯物を畳むのを手伝ってもらうなど、年齢や発達段階に応じてできることをお願いしてみましょう。最初はうまくできないかもしれませんが、繰り返し行うことで、徐々に上達していくはずです。この過程で、子どもは「できた!」という達成感を味わい、自己肯定感を高めることができます。
遊びや日常生活の中で、子どもが「挑戦」できる環境を積極的に作ってあげましょう。
ありのままを受け止めて認める
子どもの非認知能力を育む上で、ありのままを受け止め、認めることは非常に大切です。子どもは、親から認められ、愛されていると感じたいという強い欲求を持っています。親から無条件に愛されているという安心感が、子どもの自己肯定感を高め、さまざまなことに挑戦する意欲を育みます。
具体的には、子どもの長所を具体的に褒めることが重要です。例えば、絵を描くのが好きな子どもであれば、「色の使い方がとてもきれいだね」や「細かいところまで丁寧に描けているね」など、具体的な部分を褒めてあげましょう。
また、子どもが失敗したときこそ、親の温かい言葉がけが必要です。失敗しても、努力した過程を認めましょう。親に叱られることを恐れて挑戦することをためらってしまうと、非認知能力の育成を阻害することにつながります。
大切なのは、結果ではなく、子どもの頑張りを認めることです。結果が伴わなくても、努力した過程を褒めてあげることで、子どもは「自分は頑張ればできるんだ」という自信を持つことができます。
自分で考え、行動する機会を増やす
子どもが自分で考え、行動する機会を増やすことは、非認知能力、特に問題解決能力や自己肯定感を育む上で非常に重要です。子どもに選択の機会を与え、その決定を尊重することで、主体性を育み、責任感を持つことを促します。
例えば、休日の過ごし方や、夕食のメニューを一緒に考えることは、子どもにとって良い経験になります。年齢や発達段階に応じて選択肢の幅を調整しながら、「今日は公園に行く?それとも動物園に行く?」「夕食はカレーライスとハンバーグ、どちらがいい?」といったように、具体的な選択肢を提示してください。そして、必ず選んだ理由もセットで聞きましょう。
まずは、子ども自身がなぜそれを選んだのか考える必要があります。子どもが自分の考えを言語化することで、考えや、やりたいことに対して頭の整理ができるでしょう。親にとっても、子どもが選んだ理由を聞くことで、子どもの思考や想いなども知ることができます。
さらに、子どもが自分で選んだ結果がどうなるかを体験することは、物事を多角的に捉える力や、意思決定する力を養うことができます。
また、選んだ選択肢の結果に対して、たとえ失敗したとしても、親はそれを責めるのではなく、何が良くなかったのか、次はどうすればいいのかを一緒に考える姿勢が大切です。このプロセスを通して、子どもは試行錯誤しながら問題解決能力を高めていくことができます。さらに、自分の選択が尊重され、受け入れられる経験を通して、自己肯定感も育まれていきます。
非認知能力を育む上での注意点
非認知能力を育む際には、いくつかの注意点があります。
- 一方通行なコミュニケーションにならないようにする
- 努力の過程を親が把握する
- 他の子と比較しない
それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
一方通行なコミュニケーションにならないようにする
親は無意識のうちに「子どものため」と思って子どもの意見を聞かないまま、答えをすぐに提示したり、正解に導く指示をしてしまうことがあります。親は良かれと思っていても、このような一方通行なコミュニケーションを続けていると、子どもの「自分で考える力」が育ちにくくなります。
親が一方通行なコミュニケーションをとってしまうと、子どもは常に親の指示や答えを待つようになり、自分で考えて行動する機会を失ってしまい、自分の意見を持てない指示待ち人間になってしまう可能性があるのです。
子どもが何かで困っていたり、悩んでいる時に、すぐに答えを教えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、子ども自身で解決策を見つけ出すように促してみましょう。
努力の過程を親が把握する
子どもを褒めるとき、「テストで100点を取ってすごいね!」と結果だけを褒めるのではなく、「毎日コツコツ勉強したから100点が取れたんだね。頑張ったね!」と努力によって結果が出たことを伝えるようにしましょう。そのためには、子どもの努力の過程を親が把握しておく必要があります。努力の過程を把握した上で褒めることで、子どもは努力することの大切さを実感し、自己肯定感を高めることができます。
努力の過程を把握するためには、日頃から子どもとコミュニケーションを取り、何に興味を持っているのか、どんなことに取り組んでいるのかを知ることが重要です。子どもが勉強や習い事、遊びなどに取り組んでいる様子を注意深く観察し、頑張っている点や工夫している点を具体的に見つけて言葉にして伝えましょう。
また、子どもがうまくいかないときにも、努力の過程を認めることが大切です。「今回はうまくいかなかったけれど、一生懸命練習したね。たくさん頑張ったね。」と励ますことで、子どもは失敗を恐れず、再び挑戦する意欲を持つことができます。
他の子と比較しない
それぞれの子どもは個性や成長速度が異なり、得意なことも違います。他の子どもと比較することは避けましょう。比較によって、お子さんの自己肯定感を傷つけたり、劣等感を抱かせたりする可能性があります。また、他人との比較ばかりしていると、子どもは本来の自分の良さを見失い、目標を見つけるのが難しくなるでしょう。
一方で、過去の自分と比較して成長できたと実感することは、自己肯定感を高める上で効果的です。例えば、以前は難しかった縄跳びの二重跳びができるようになった、計算ミスが減ったなど、小さな成長でも良いので、具体的に褒めてあげましょう。「前はできなかったのに、すごいね!」「努力した成果だね!」など、頑張りを認める言葉をかけることで、子どもは自信をつけ、さらに挑戦する意欲を持つようになります。
他の子どもと比較するのではなく、お子さん自身の成長に目を向け、努力や進歩を認め、励ましていくことが大切です。
「深めるコミュ力」で子どもの非認知能力を高めよう

非認知能力を育むためには、親子間の深いコミュニケーションが重要です。そのためにおすすめしたいのが「深めるコミュ力(深コミュ力)」です。
深コミュ力を実践することで、子どもは自分の気持ちや考えを言葉で表現できるようになり、親は一方通行のコミュニケーションを解消し、子どもに寄り添う声がけができるようになります。
「まずは10分 親子の対話で深めるコミュ力」ドリルでは、親子で考えや気持ちを言葉にして伝え合う練習、正解にとらわれず自分の答えを見つける練習を通して、「考える力」、「言葉にする力」、親子共に「質問力」を身につけることができます。
毎日少しでも時間を作り、親子で深コミュ時間(タイム)を実践することで、子どもの非認知能力は着実に育まれていきます。
「まずは10分 親子の対話で深めるコミュ力」ドリルは、オンライン・書店で購入いただけます。以下のURLから未就学用無料体験版もダウンロードできますので、ぜひご利用ください。